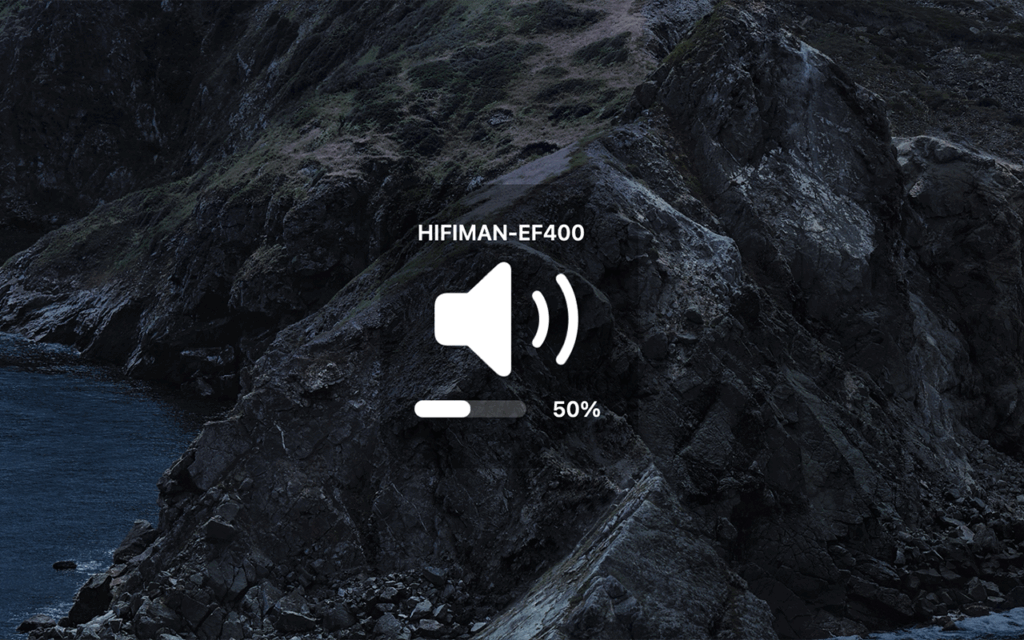 Mac
Mac MuteHUD 1.4とFFTranslateのセール
ミュートとボリュームのHUD表示ユーティリティ「MuteHUD」を1.4にアップデートしました。おそらく既知の問題だったと思うのですが、現在の再生デバイスではなく、それ以外のデバイスのボリュームを変更した場合もボリューム変更のHUDが表示さ...
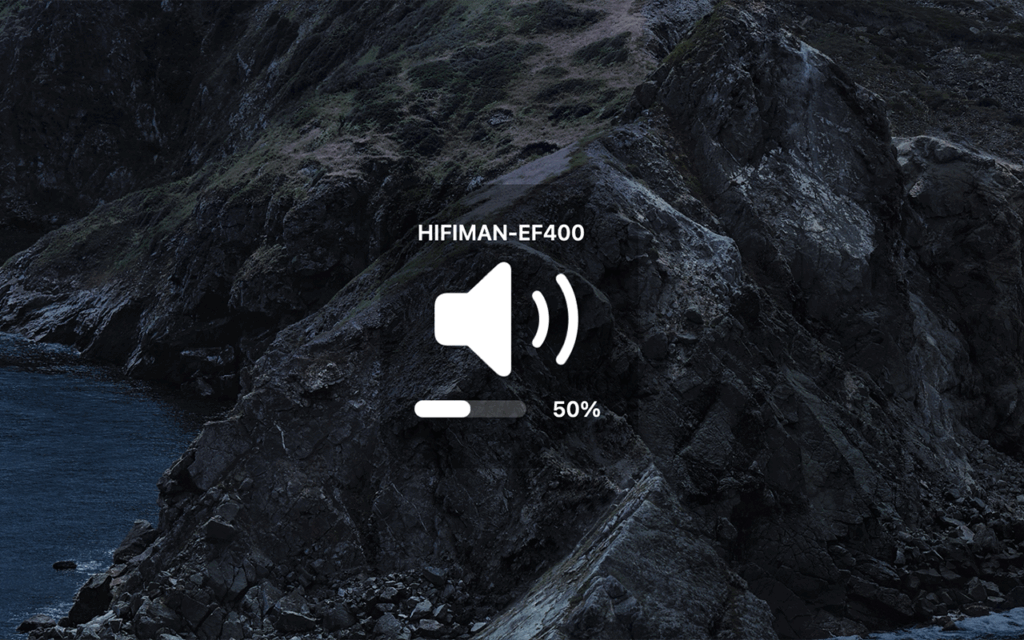 Mac
Mac  Audio
Audio  Electronics
Electronics  Audio
Audio  その他
その他 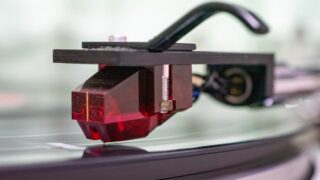 Audio
Audio  Audio
Audio 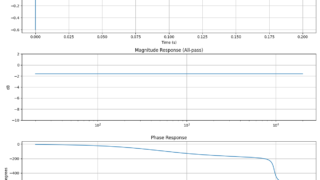 Audio
Audio  Electronics
Electronics  Electronics
Electronics