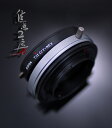304月
家電量販店にオリンパスの高倍率コンデジ「SZ-20」が展示されていたので、チラッと触ってきました。
まず第一印象は「予想以上に薄い、小さい」ですね。
Webで写真を見ていると、SP-800UZみたいな従来の高倍率機をちょっと小さくしたくらいというイメージを抱きがちですが、実際は普通のコンパクトをちょっと大きくした程度のコンパクトさです。
グリップがしっかりしているのと、ストロボを格納しているレンズ上部分が飛び出してるので、写真だと大きく感じてしまうんでしょうね。
多少誤差はあるかもしれませんが、カタログ数値からμ-9010とのサイズ比較をしてみました。
これを見てもらえるとコンパクトさがだいぶ分かっていただけるかと。
実際に触ってみた感じでもこんな印象に感じました。
使い勝手の面では過去のμシリーズと比べて液晶表示のUIが断然速くなっていますね。
シャッターレスポンスやズームなどの機械的な動作も快適でした。
XZ-1もそうですが、最近のオリンパス機は本気だなぁと感じますね。
12.5倍ズームもカタログ数値だけでなく、ワイド端もテレ端も液晶画面で見る限りとはいえ、描写がしっかりした印象でした。
テレ側でもマクロが90cmまで寄れるということですが、実際にはもうちょっと寄れる気がしました。
ただこの点では上位モデルのSZ-30MRはもっとすごくて、テレ端も40cmになっているようです。
なお、SZ-20とSZ-30MRの大きさの差はアスキーの記事で確認できます。
あと、ストロボが大きめで、しかも手動でポップアップする形式なのが良い感じです。
非発光の設定を間違えることがないというだけでもずいぶん使い勝手は良くなりますからね。
SZ-30MRとどちらを選ぶかは難しいところですが、SZ-30MRになると価格的にXZ-1とも近づいてくるでしょうし、通常用途ならSZ-20も十分かと。
いずれにせよ、この3モデルはどれを選んでも良い感じだと思いますけどね。
Filed under: DigitalPhoto
274月
AdobeのRAW現像ワークフローソフト「Lightroom 3」が3.4にバージョンアップしています。
今回もカメラ機種の追加が主な変更点ではありますが、それ以外の変更も結構たくさんあるようです。
私が気になった主なものはこんな感じです。
・トーンカーブのポイント調整で上/下矢印キーが正しく機能しない
・セカンドウィンドウ有効時にマウス操作でCPU負荷がかかる
・検索時にスペースが含まれていると候補キーワードが正常動作しない
・キヤノンM-RAWでハイコントラストエッジに斑点やマゼンタかぶり
・iPhoneで撮影したビデオの撮影日が1903年12月31日になる
・Nikon D7000 / PENTAX K-5の多重露出でマゼンタかぶり
・カラーノイズ軽減値がプリセットに正しく保存されない
どれもこれまで気になったことはないんですが、カラーノイズ低減のプリセットは私も良く使ってるので、気づかないだけでこれまでもおかしかったのかも。
カメラの方は以下の機種への対応が追加されています。
OLYMPUS E-PL2 / E-PL1s /XZ-1
Canon EOS Kiss X5 / EOS Kiss X50
Kodak Z990
Samsung NX11
Nikon D5100
Hasselblad H4D-40
FUJIFILM FinePix X100 / S200EXR / F550EXR / HS20EXR
XZ-1やFinePix X100あたりをお使いの方には朗報ですよね。
うちにはそんな新しい機種はないけど、バグ修正も入ってますし、早速アップデートしておきました。
Filed under: DigitalPhoto
264月
銀塩では一時代を築いた「YASHICA」ブランドですが、デジタルでもエグゼモードのトイデジで復活していたのですが、再び撤退することになったようで。
京セラのカメラ撤退後、香港のJNC Datum Tech Internationalにブランドが写り、そこからエグゼモードで使われてたんですが、aigoの輸入を始めるにあたり整理した、といったところでしょうか。
同時にAGFA PHOTOの輸入もやめるようですし。
まぁ、AGFAにしろYASHICAにしろ、本来のブランドとはずいぶんかけ離れた使われ方だったので、ブランドを使う意味があまりなかったんでしょうね。
そもそもヤシカを知ってる世代へのアピールはほとんどないに等しい感じでしたし。
商標権は再びJNC Datum Tech Internationalに戻るようですが、もう復活はないかなぁ。
ちなみに、CONTAXのほうは基本的にツァイスが商標権を保有しているようです。
京セラは身飾品などのカメラとは違う分野で商標権をまだ持ってるみたいですけど。
できればコンタックスは復活させてほしい気もしますが、名ばかりのブランドでは結局ダメなんですけどねぇ。
Filed under: DigitalPhoto
224月
オリンパスの高級コンデジ「XZ-1」のファームウェアが1.2に更新されたようで。
どんな機能拡張なんだろう?と思ったら、縦横方向記録が追加されたんだとか。
なんだか最初からあってもおかしくない機能ですねぇ。
そもそも物理的なセンサーは中に入ってるわけでしょうし…。
再生時にコントロールリングで画像の向きを回転できるのは便利そうですけどね。
あと、ファームウェアのアップデートには「デジタルカメラアップデーター」を使うんだとか。
以前のOLYMPUS Masterよりは使いやすいでしょうけど、相変わらずパソコンとつなぐやり方なんですね。
なんだかイマイチな感想になってますが、XZ-1自体はとても気になっています。
所有されていらっしゃるブロガーさんの写真を拝見しても、かなり良い感じなんですよね。
大きさを考えるとGF1とそれほど変わらないのかもしれませんけど、オリンパスの本気が詰まってる気がします。
それだけにバグ修正みたいな変更だけでなく、地道な機能アップをしてロングセラーにしてほしいところです。
Filed under: DigitalPhoto
174月
富士フイルムの薄型コンパクト「FinePix Z900EXR」が店頭に並んでいたので、チラッと触ってきました。
Z700EXRは今でも結構使っていますし、Z800EXRもお借りしたことがあるので、気になってたんですよね。
カメラらしいガッチリした機種も好きなんですが、普段使いにはこういう携帯しやすい屈曲系コンパクトもお気に入りなんです。
持ってみてまず最初の感想は「ほんの少し薄くなったかも」というところ。
スライドカバーがやや平面的になった分、薄くなったような感じです。
カタログスペックを見ると、2mmくらいだそうで、確かに体感もそんなくらいの差ですね。
使い勝手の部分では背面の液晶脇にHOMEボタンができたのが新しいですね。
iPhoneやスマートフォンなどのUIを意識したのかなぁという配置ですね。
タッチパネルのUI自身もスマートフォンを意識してあって、特に再生時の写真操作は初期のタッチパネル機と比べるとずいぶん使い勝手が良くなったように思います。
撮影時もタッチAFやタッチ後の自動追尾など、タッチパネルのメリットを活かす内容に仕上がっていますね。
画質に関してはいつものように店頭&液晶での確認なので詳細はわかりませんが、28mm相当のスタートになったのは便利になるでしょう。
1600万画素に増えたのはちょっとどうかなぁと思いますが、裏面照射になったのは大失敗写真は低減できるのではないでしょうか。
あと、EXR CMOS採用に伴って、Z800EXRに鳴り物入りで採用されたはずの瞬速フォーカスは内容が変わっています。
Z800EXRは素子上にAFセンサーがある位相差ハイブリッド方式だったのですが、Z900EXRではX100と同じEXRプロセッサとCMOSの高速処理によるスピードアップ(内容は通常のコントラスト方式)となっています。
カタログスペック上はZ800EXRの0.158秒がZ900EXRでは0.16秒ですが、実際に使った感じではやはりZ800EXRのほうが「瞬速」だったかな。
ただ、Z800EXRは常に位相差というわけではないので、AFスピードにはムラもありましたし、安定した速さという意味では実用上支障がない程度の差だと感じました。
Z700EXRから買い換えるか?と言われると、まだそこまでではない気もしますが、それ以前のxDカード機あたりからなら、ずいぶん新しさを感じられるのではないかと思います。
ただ、Z800EXRもずいぶん安くなってるので、そのあたりが難しいところですけどねぇ。
Filed under: DigitalPhoto
094月
先日ゲットしたデジカメ「FinePix 4900Z」の試しどりをしてみました。
デジカメの世界ではすでに年代物になってる機種ですが、動作は問題なしです。
多少、AWBが弱いあたりが年代を感じますが、LightroomでJPEG現像してしまう手もありますし、マニュアルでホワイトバランスを決めてあげるのも良いですね。
そもそもメモリカードが32MBなので、のんびりゆっくりペースで撮れましたし。
あとは標準のままだと、ややシャープでコントラストが強めな印象もありました。
プリントを前提とした仕上げになってるんでしょうね。
次回撮る時はそのあたりをちょっといじってみたいところかも。
そういったカスタマイズから露出補正に各種優先AE、さらにリングでのMFまで高機能なのも当時の高級機種ならでは、です。
反面、やや気になったのはノイズの多さかな。
ISO125が基準感度なんですが、カラーノイズがやや目立ちました。
わりと大型でゆとりのある撮像素子なので、もうちょっと少なめかなぁと思ってたんですけどね。
まぁ、最近のモデルも画像処理でノイズを潰してるだけで、素材にはかなりノイズが乗ってるようですが。
そこら辺はDfine 2あたりでなんとでもなることですし。
ということで、概ね好調な良機でありました。
これだけを持ち歩くのは多少不安もありますから、最新のデジカメとペアで持ち歩いてあげようかと思います。
Filed under: DigitalPhoto