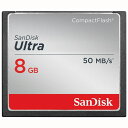036月
いまだにメイン機として活躍してくれていたソニーの一眼レフ「α700」ですが、庭で使っていて、なんだかマクロレンズのフォーカスリングが回らないなぁと思い、部屋に戻ってレンズを調べようとしたら、ミラーボックスに見慣れない破片が。
#慌てて写真を撮り忘れた…。
形状的にこれはレンズじゃなくカメラの部品だなと、ミラーボックスの中を良く眺めてみるとミラーの下側が全然支えられてない状態に。
念のため、ネットでも調べてみると「主ミラー押さえ」という部品のようで、たぶんそのまま放置していたら、ミラーが脱落すると思われます。
CONTAXなんかではミラーが両面テープで貼ってあって、徐々にズレてきたりしましたけど、おそらくアレより脱落のペースは早いでしょうねぇ。
元々がどうやって留めてあったかは不明ですが、部品の端が少し欠けてもいましたので、もうココはボンドしかないなと。

で、接着した結果が上の写真であります。
たぶんこれでミラーが落ちてくることはないのかなぁと思いますが、微妙にミラーがズレて、ピント精度が落ちてる可能性はあります。
2008年に導入してますから、すでに8年も使っているんですね。
多少出番が減ってるここ最近の16ヶ月でも約7000枚撮ってるのを確認しましたので、おそらくこれまでだと5万枚くらいは撮ったでしょう。
シャッターユニットの耐久性能は10万枚くらいいけるっぽいですけど、さすがにもう修理するのも…。
ということで、しばらくはNikon D300をメインにしてみようかと。
レンズの充実度という点ではほぼ同等なんですが、こっちはAFレンズの手持ちが少ないのと、本体内手ぶれ補正がないので、室内の「ごはん写真」を撮るのに不向きかなと思ってあまり使ってなかったんですよね。

ただ実際に撮ってみるとISO3200まで上げる設定にしてあるのもあって、意外と平気でした。
カメラ本体がずっしり重いのも手ぶれを防ぐのに良いのでしょうし、そもそもちゃんとグリップするクセが付いて良いのかも。
さらにAWBがα700よりも優秀なおかげで、撮影や現像が楽なくらいでした。
ただ一応、α700も今は問題なさそうなので、うまく併用しつつ、次期メイン候補もそろそろ考えないといけないでしょう。
調べた限りではα55や77、あるいはα7の初代以外などが順当な後継でしょうか。
あえてα900とか、PENTAXに移るなんてことも考えてますが、D300が元気なうちはなかなか重い腰が上がらないかもしれません。
Filed under: DigitalPhoto
065月
世の中はすでにSDXCやXQDに移ってきていますが、今更ながらコンパクトフラッシュを買い足すことに。
というのも最近、紗羅がOLYMPUS E-300をまた使い始めたのですが、それに入ってたのが512MBで、さすがにちょっと少ないなぁと。
私の手持ちも4GBが2枚だったので、それを強化する意味もあります。

ただ私が予想していたより意外に値段が下がってないんですね。
16GBになるとSDHCとかだと64GBが手に入りそうなお値段なので、8GBで妥協しました。
その代わり、一応メーカーもののSandisk Ultraです。
Sandiskは偽物も多く出回っていますが、今さらこのクラスのコンパクトフラッシュに偽物はないかな?

速度は最大読取り速度が50MB/sで、333倍速ということだそうです。
α700用にこれまで使っていたSandisk Ultra IIは2004年製だったようで、書き込み速度が9MB/sec以上、読み込み速度が10MB/sec以上と当時の記事に書いてありました。
速度は5倍くらいになってるわけで、たしかにα700でも保存時間がかなり短くなったのを体感できました。
で、E-300にはこのSandiskの4GBを移動させました。
トランセンドは512MBの80倍速だそうですから、速度はかえって遅くなってるくらいかも。
とはいえ、やっぱり容量が多いほうが安心して撮れますし、もしどうしても遅いようなら、Nikon D300に入ってる133倍速のほうと交換しても良いかなと思っています。
Filed under: DigitalPhoto
161月
FUJIFILMから新しいミラーレスカメラのフラグシップモデル「X-Pro2」が2/18に発売されるそうで。
X-Pro1が出たのが2012年ですから、4年経っての待望のニューモデルということになりますね。
2000万画素超となった「X-Trans CMOS III」に注目が集まりがちですが、どうやら凄いのは画像処理プロセッサの「X-Processor Pro」のほうみたいで、これにより色々な処理速度、フィルムシミュレーションなどの画像処理機能が改善されているようです。
逆に言えば、従来モデルはもうファームウェア更新では追いつけないくらいの差になったからこそ、のモデルアップデートということなのでしょう。
私が他で気になったのは以下の3点です。
・ファインダー映像の表示速度を85fpsに向上
・SDカード用のデュアルスロット
・最高速1/8000秒、最速同調速度1/250秒のフォーカルプレーンシャッター
いかにも今っぽいソフトウェアや見た目の部分ではなく、撮影機材としての基本となる部分を改善してきているな、というところに好感が持てます。
他社のフラグシップに比べればお値段も20万円くらいと格安(?)ですし、レンジファインダースタイルに抵抗のない、いやむしろこっちが良い、という方にはかなりおススメのニューモデルではないでしょうか。
いやもちろん、旧モデルたちの価格も気になりますけどね。
Filed under: DigitalPhoto
061月
NikonからFXフォーマットのフラグシップ一眼レフ「Nikon D5」が3月に発売になるそうで。
同時にDXフォーマットのフラグシップモデル「Nikon D500」も発表されています。
D500は25万円くらい、D5は75万くらいと3倍の価格差がありますが、やっぱり今となってはFXフォーマットにどうしても注目してしまいますね。
共に画素数は2000万画素ちょっとで、ニコンとしては画素数競争はもう不要という考えのようです。
プロフェッショナルモデルとしてはやはり歩留まり重視なのでしょう。
D5は常用感度が最大ISO102400まで対応させていますし、AFの大幅な強化を図っているように見えます。
また4K動画の対応にも力を入れていますが、4K動画は等画素記録となるようで、実質的にDXとほぼ同じ画角となるんだとか。
FXで動画撮影するとフルHDか720pということで、なんだかやや勿体無い気もしますが、本体内で画像処理するにも限界があるという面もあるのでしょう。
あと、面白いところではXQDカード対応モデルとCFカード対応モデルの2種類が用意されるというところでしょうか。
ダブルスロットなら、XQDとCFに対応したモデルもあったら嬉しいような気もしますけど、そこはプロ向けですから、どちらかで統一したほうが扱いやすいんでしょうね。
他にも意外なところでは本体に有線LANが装備されているのがスタジオ撮影では結構役立ちそうな気がしますし、グローブのままでも操作できるというタッチパネルもUIも含めて気になるところです。
比較明合成や比較暗合成も新たに追加されていて、こういうのは後でソフトウェアでやれば良いようなものの、作品はカメラ本体で完結させたい方には喜ばれる機能なのかなと思いました。
Filed under: DigitalPhoto
186月
リコーからAPS-C素子採用のコンパクトカメラ「RICOH GR II」が7/17に発売になるようで。
おそらく皆さんも期待していたマクロの強化はされず、バッファ強化とWi-Fi機能搭載が主な変更点のようです。
マクロは先日のライカQのような手動繰り出しでも良いと思うんですけど、サイズ的にそんな機構を入れるのも厳しいのかな。
ちなみに、過去の例からすると、AWBあたりは従来モデルもファームウェアで対応しそうな気がします。
そういうところはリコーGRの良さですし、購入への安心感にもつながっていると思うので、ぜひ継続してほしいと思います。
少しご無沙汰気味だったカメラも最近またチェックするようになったのですが、意外と価格が下がっていなくてビックリしました。
売れているかといえばそうでもないようですが、コンデジでも結構なお値段を維持してるんですね。
逆に使われなくなった昔のコンデジの中古はどこに行ったんだろうというくらい、数が少ないですけど、やっぱり海外かなぁ。
メイン機種もサブのコンデジもだいぶ古くなってきたので、リプレースも考えているのですが、なかなか思ったようなモデルに出会えていません。
メインは非ベイヤー、サブは大きめの素子で寄れるものをという、意外にシンプルな要求だと思いますが、合致するものがもっと増えてくれたらなと願っています。
Filed under: DigitalPhoto
116月
ライカから35mmフルサイズのCMOSセンサーを搭載したレンズ一体型カメラ「LEICA Q」が6月末に発売だそうで。
SUMMILUX 1:1.7/28 ASPH.搭載ですから当然ながらお値段も60万円弱とそれなりの価格です。
Mマウントのズミルックス28mmの実売価格がF1.4とはいえ、80万円以上するわけですから、むしろ35mmフルサイズの2400万画素CMOSセンサーのカメラが付いてくると考えるべきなのかも。
ただちょっと変わってるのはマクロにもうまく対応しているところで、レンズの根元に用意された「MACRO」リングを回転させることでレンズを繰り出してマクロモードに突入するという、他のメーカーではちょっと企画が通らないような仕様になってます。
広角レンズなので全群繰り出しみたいな形で画質がしっかり確保できるのか、それとも一部レンズだけが繰り出されるのかは分かりませんが、接写にある程度対応できているのは実用上は便利でしょう。
こんな仕様の反面、光学手ブレ補正やWi-Fi、NFCなどにも対応しているのが不思議なバランスです。
バッテリーが高倍率ズーム機のV-LUXシリーズと共通という点から考えると、開発にはかなりPanasonicが関わっていると推測されますが、どうでしょうか。
マイクロフォーサーズを展開するPanasonic自体が35mmフルサイズ機を出すことはないでしょうけど、これのPanasonicバージョンが出たら、それまた面白そうな気もします。
Filed under: DigitalPhoto