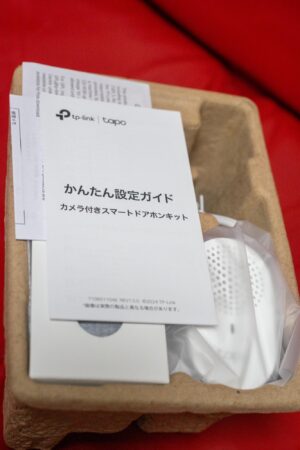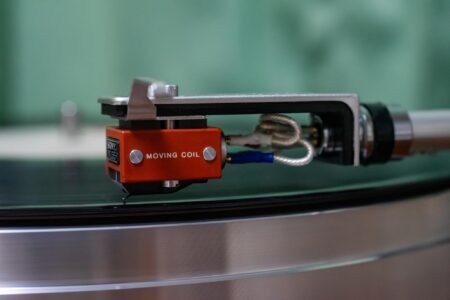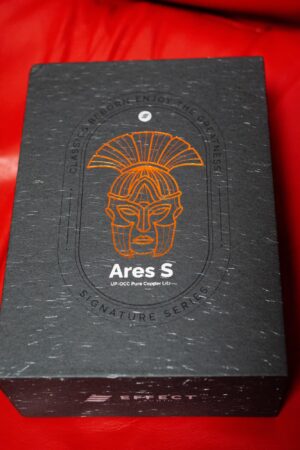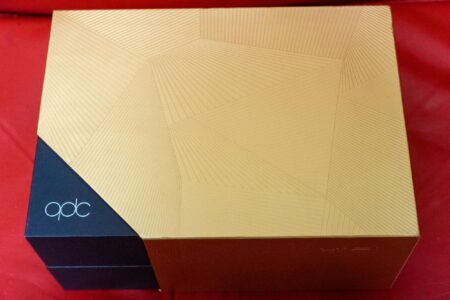t-linkのカメラ付きスマートドアホンキット「Tapo D210」を導入しました。

最近「近所で工事するので…」とか「屋根の釘が抜けてますよ」といった下見っぽい人がそこそこウロウロしているので防犯も兼ねてカメラ付きのものを物色していて新製品のこちらを見つけました。
荷物受け取りで置き配もイヤだけど、ずっと待機状態というのも困るから、というのもありますけどね。
元々は門柱にPanasonic(実際はNational)の会話できるやつが付いてますが、どこかで配線or室内側ユニットなりが壊れているらしく引っ越してきた当初からちゃんと動きませんでした。
それでREVEXのリモートチャイムを導入したのが8年半くらい前で、これも十分便利ではありましたが通話はできず屋内側はわりと早く電池が切れる(5V ACアダプタを用意すればそれでも対応可)ので、上記の防犯も兼ねてそろそろ置き換え時期かなと。

上位モデルの「Tapo D230S1」ともそこまで価格差がないので迷いましたが、若干のカメラ解像度は違うものの基本的な機能は同じです。
D230S1は有線LAN対応のハブとカメラがSub-1Gの868MHzでつながり、ハブからルータ経由でスマホ等にWi-Fiでつながる形ですので、カメラとスマートチャイム双方がWi-Fi接続するD210のほうがシンプルで良いかなと。

スマートチャイムは写真だと電源が何を使うのか不明だったのですが、直接ACに挿すACアダプタ的な形状で写真で見るよりちょっと大きめです。
あくまでチャイムでこれとカメラで通話はできないので、そこはサクッと応対ができないのはもったいないかも。

壁への取り付けはリモートチャイムと大差はなく、ネジ2本あるいは両面テープで固定する形です。
ネジがちょっと長すぎるようにも思えましたが、取り付けベースごと持っていかれると盗難アラームも鳴らないのでしっかり固定しろということでしょう。
設営自体はそこまでややこしくはなく、スマホアプリの指示に従ってステップを踏んでいけば大きな問題はありません。
TP-Link IDを取得してアクティベートする必要がありますが、そのメールが迷惑メールに振り分けられていたことと、Wi-Fiは2.4GHz帯のWPA/WPA2しか接続できないのが注意点なくらいでしょうか。
WPA2についてはその後、ちょっと苦労するんですけどね。
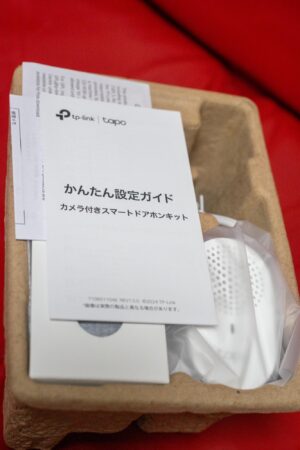
ファームウェア更新もスマホアプリ経由でやってきて1.0.12にしておきました。
動き検知は人物検知のみみたいな記載もありますが、ちゃんと動体検知、車やペット検知も選べます。
他のtp-link製品も含めて同じアプリで一元管理できるのも良いですね。
ただ、録画された動画のダウンロードに失敗することが多かったり、電波強度が弱いと録画された動画の閲覧にちょっと待たされる(そもそも今のカメラ表示を経由しないと録画閲覧に行けない導線なのも)のはやや難点ではあります。

2.4GHz帯なのでそこそこ平気かなと思ったのですが、玄関の外側(当たり前)に設置するのでやはり思ったよりも電波強度が弱めでした。
大元のWi-FiルータからだとRSSIで-70前後で雨が降ると繋がらなかったりでした。
そこで以前使っていたルータを引っ張り出してきて、中継器として玄関に設置してみましたがなぜか大元のルータのほうにつながってしまう現象に悩まされました。
リセットして最初からセットアップすると途中でWi-Fi強度を確認する画面が出てくるのですが、そこではちゃんと中継器を指して十分な強度になってるのに設定を済ますとやっぱり大元に繋がります。
結果としては中継器側がおそらくWPA3(大元はWPA2にしてある)になっていたようで、別のアクセスポイント名にして明示的にWPA2で中継器のみにつながる形としました。
これならRSSIは-42くらいでバリバリ入ります。
そもそもWPA3には対応してほしい気もしますけど、そこはちゃんと仕様にも明記されているので仕方ないですね。
使い勝手としてはこれまでのリモートチャイムとそんなに違わないというのが正直なところです。
「ピンポーン」と鳴ったらスマートフォンでわざわざ応答するより早く玄関に行ったほうが…と思ってしまうのもあるでしょう。
そもそもドアホンが押される前に車の音に反応して動き始めちゃうというクセが抜けないのもあります。
また人物検知は当たり前ながら住民にも反応するので、郵便物を取りに行くとか、車で出かける時も通知が来てしまいます。
そこはセキュリティがちゃんと動いてるなという安心感と引き換えで考えるしかないでしょう。
影が揺れたりして朝方に誤検知したりといったこともごく稀にありますが、頻度としてはかなり少ないです。
画面中の検知領域を指定できたりもするので、あまりにも多い場合はそれで除外することもできるはずです。(うちでは全領域検知で問題ありません。)
バッテリーはチャイム下側のUSB-Cで充電できるので、昼前にモバイルバッテリーで補充するようにしています。
ベースから外すのにはSIMカード取り出しよりちょっと太めのピンを差し込む必要がありますし、盗難アラームをオフにしたりする必要もあるので、このやり方が面倒が少ないかなと。
最初の頃はWi-Fiが弱かったり試行錯誤もあって1日に数%バッテリーが減って(その際はバッテリーの減りが早い旨の通知もちゃんと来る)いましたが、設置から15日ほどで84%です。
ちょっと多めの来客や外出でも1日で1%減らないくらいなので、カタログスペックの180日間は多少長めとしても100日くらいは十分動作すると思われます。
あとは温度変化や雨の降り込みなどでどのくらい耐久性があるかですが、むしろSDカードのほうが先に音を上げるくらいでしょうか。
セキュリティの観点では他のカメラや温度計、センサーなども追加してみても良いかなと思ってますけど、そっちは電源が別途必要だったりハブが必要だったりするのでひとまずドアホンで様子見してみる予定です。
Tapo(タポ)
¥8,900
(2025/02/01 15:23:12時点 Amazon調べ-詳細)